昨日から報道で、「愛知県の大村知事のリコール不正署名事件 リコール団体の事務局長を逮捕」といった記事が多くみられます。
昨日、テレビを見ていて速報で出てきました。以前から報道のあった案件ですが、報道の中で出てきた「地方自治法違反」という言葉が少し気になったので書いてみます。
地方自治法違反
報道の内容は、大体以下のような内容でした。
愛知県の大村知事へのリコール不正署名事件で、警察は先ほど、リコール運動の事務局長、田中孝博容疑者(59)を地方自治法違反の疑いで逮捕しました。
大村知事のリコール運動の事務局は、県の選挙管理委員会におよそ43万5千人分の署名を提出しましたが、8割以上が「無効」とされました。
その中には自分で署名していないものや、すでに死亡した人の名前が多数あったことなどから、警察は、署名が偽造された疑いがあるとみて捜査を続けていました。
メーテレさんのホームページより
そして、テレビの解説や社説で多く出てきた言葉が、「民主主義の根幹を揺るがすもので絶対に許されない行為だ。」というものでした。
そこに関しては、その通りだと思いますし、絶対許されない行為だと考えます。当然の考え方ですよね。しかし、なんとなく、自分自身でそのこと自体を確認したくなり、少しだけ調べてみました。
地方自治法違反は間違いないのでしょうが、どこかそれ以前に考えないといけないものがあるような気がします。
法令の確認と「住民の意思の正当性」ということについて少し考えてみます。
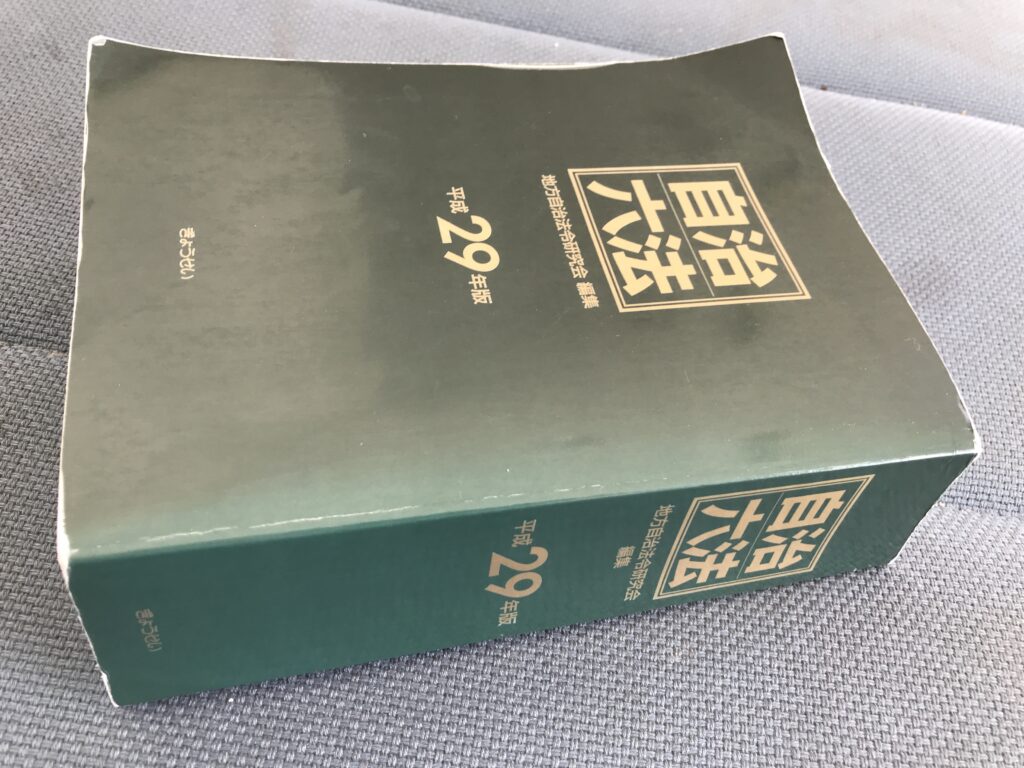
地方自治法の規定
まずは地方自治法の法令から確認してみます。首長に関するリコールの法令は以下の通りです。
第81条(地方自治法)
1 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。
2 第七十四条第五項の規定は前項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項から第八項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は前項の規定による請求者の署名について、第七十六条第二項及び第三項の規定は前項の請求について準用する。
地方自治法
まず、1項で長のリコールについて規定し、2項で条例制定などの場合の条文を規定し、罰則なども準用されることが示されています。
冒頭で、紹介した「愛知県の大村知事のリコール不正署名事件」の場合、この規定の適用が考えられているわけです。
では、次に参考までに、過去に発生した首長のリコールの例を見てみます。
過去のリコール事案
過去の首長のリコールの例は以下の通りです。
| 年月日 | 首長名 | 自治体名 | 結果 | その後 |
| 2006年2月19日 | 小林正明 | 神奈川県城山町長 | 成立 | 不詳 |
| 2009年3月29日 | 岡野俊昭 | 千葉県銚子市長 | 成立 | 次の選挙で敗れる。 |
| 2009年8月9日 | 谷育造 | 栃木県岩舟町長 | 成立 | 不詳 |
| 2009年12月27日 | 小川利彦 | 千葉県本埜村長 | 成立 | 不詳 |
| 2010年12月5日 | 竹原信一 | 鹿児島県阿久根市長 | 成立 | 次の選挙で敗れる(2011年阿久根市長選挙)。 2015年・2019年の同市長選にも敗れる。 |
| 2012年3月18日 | 佐藤公敏 | 静岡県川根本町長 | 不成立 | 不詳 |
| 2012年10月21日 | 石田寿一 | 山梨県西桂町長 | 成立 | 下記の同町議会解散請求とのダブルリコールの成立。 |
| 2017年10月8日 | 相馬宏行 | 静岡県河津町長 | 成立 | 次の選挙で敗れる。 |
私の場合は、2010年の竹原信一さんのケースが印象的でした。リコールだけに限らず、いろんな話題を提供してくれた方でした。
こうしてみると色々なケースがあるようですね。それぞれにその地方の事情があったのだろうなと想像してしまいます。

住民の意思を考える
地方自治について考えてみると、住民自治はその根幹をなる考え方であり、住民自治を具現化するためにほんとはみんなで考えるのが良いが、それは現実的でないために、代表的民主主義の制度が活用されています。
その仕組みが選挙であり、それを使って、住民の意思が担保されることになります。首長や議員はこうやって住民意思の代表として政治を行うことになるわけです。
当然、住民の意思を具現化しないといけないわけですが、時にはみんながそうじゃないと感じるケースが出てきます。それを補完するものとして、地方自治法はこういった制度を準備しているわけです。
まとめ
ここで、今回の「愛知県の大村知事のリコール不正署名事件」の場合を考えてみます。行われたであろう不正行為は許されるべきものではありません。
今後の当局の捜査で、真実が解明され、罰すべき人は罰するべきだろうと思います。しかしながら、なぜこんなことがおこったのか、ここで考える住民の意思とはどういったものだったのかについて、どうしても思いが行ってしまいます。
住民の意思だといって、何かの制度を使用する場合に、その前段の首長を選出する段階での住民の意思とはどんなものだったのかと思ってしまいます。
その前の「住民の意思」というと「選挙」ですよね。ここでの、住民の意思が本当の意味でのそれだったのか、投票率の話を持ち出すつもりはありませんが、政治への住民の参加の大切さを考えてしまいます。
「愛知県」という大都市だからこんな感じ方をしてしまうのでしょうか。
大都市だからということでなく、どの自治体であっても、本当の意味での「住民の意思」って何だろうとしっかり考える必要があるようです。
I thought about the recall and the will of the residents. The recall problem of the Governor of Aichi Prefecture was an opportunity. Residents’ will is important. I think the recall system is a necessary system for political management. However, I think it is important to confirm the will of the residents and participate in politics at the election stage before that.



